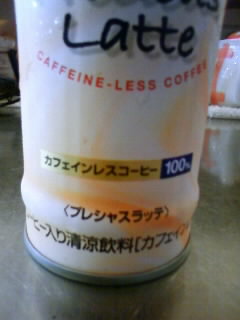昨日に続き今日は投機目的がもたらす品質低下です。
投機筋で買い叩かれたコーヒーは
1杯450円の「キリマンジャロ」コーヒーを飲む場合、3.45円が生産者の取り分、6.46円が生産国の取り分となっているに過ぎない。コーヒーの真の品質(消費者が求める有用性)は、味と香り、すなわち香味で決まる。そしてその香味は一般的に、 7割が生豆、 2割が焙煎、 1割が抽出に依存していると言う。生産国で7割の「使用価値」が付されるのにもかかわらず、生産国の取り分は上記のように1.44%に過ぎないのであり、いかに生産者・生産国にとって不当な価格形成がなされているか、実感することができよう」(『コーヒーと南北問題』189頁)
この通りの状況で買い叩かれたコーヒーは生産性重視で品種改良され種だけを生産し、それでも生産は追いつかず原価割れし、品質低下につながりました。
これは国内で近年たて続いて起こった食品の偽装問題で同じようなことがいえるのではないでしょうか?
あまりに価格に走ったため、コストダウンの限界がきてしまい偽装に走る。
まだ嗜好の問題で一部ではありますが、コーヒー業界は変化してきました。
市場価格に振り回される生産者の存在、時代背景から消費国側も危機感を持ち適正価格で高品質コーヒーを買い付ける必要性が求められるようになりました。
それが当店の扱っているスペシャルティコーヒーです。卸価格にして約2倍〜3倍は違います。
ですが、まだ現状は厳しいと思っています。
当店のように商社や生豆問屋から仕入れていると解るのですが、コーヒー豆は2次流通、3次流通があたりまえで業者が間に入っている状況です。
今では自家焙煎店が集まって生産者からダイレクトに買い付けるという方法をとっているところがあります。
この場合だと生産者も商社に買い叩かれずにすみます。
本来なら品質の高いものは適正価格で買うものだと思います。
「安ければ良い」こういう価値判断もあっていいと思いますが、コーヒーの魅力はやはり香味です。ですが買い叩かれ香味まで失ったコーヒーに魅力があると思えません。
コーヒーを通してしか語れませんが、このブログを見て「物の価値」を1度考えてもらえると幸いです。